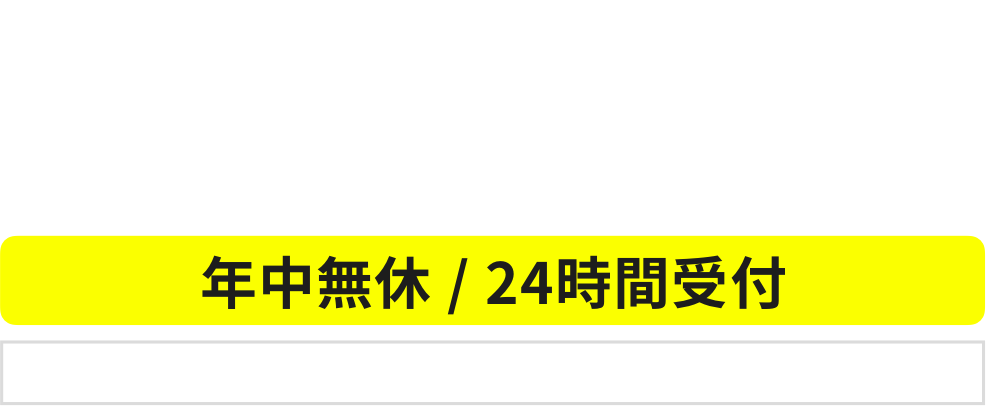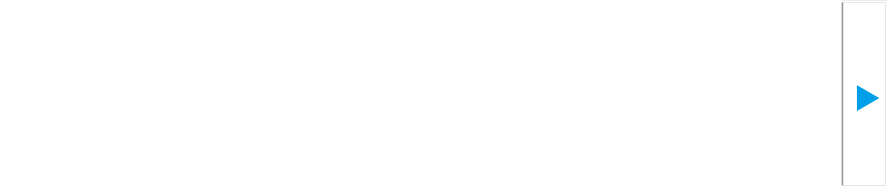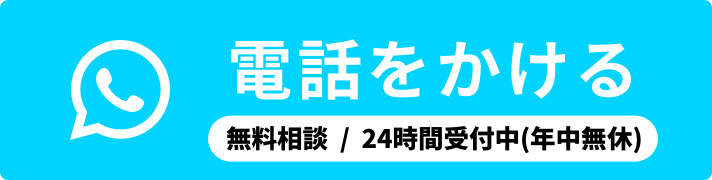気温が高い日が続くと気を付けたいのが、虫問題。自宅に虫が飛び回っている光景は、気持ちが良いものではありませんよね。
常日頃からしっかり対策をしておかないと、虫は繁殖し続け、その数は数がどんどん増えてしまいます。更に嫌なニオイも充満してしまいます。
虫にもニオイにも悩むことなく過ごすためにも、日々の対策が重要になってきます。
今回は、生ゴミに虫が発生する原因やニオイ対策について徹底解説します。快適な暮らしを手に入れましょう。
目次
生ゴミを放置するとどうなる?
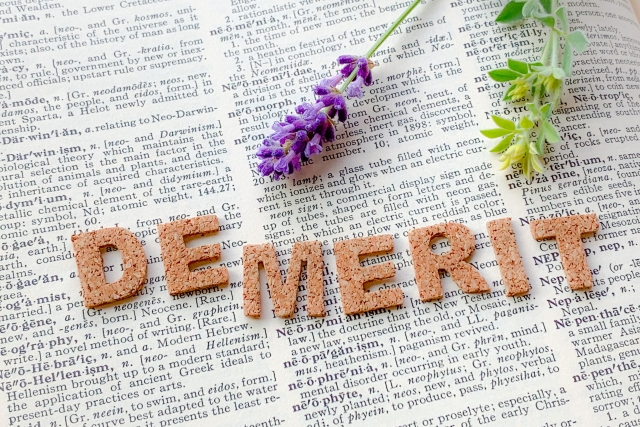
そもそも生ゴミを放置すると、どのような問題が出るのでしょうか?デメリットや問題点について解説していきます。
害虫が発生する
今回のテーマでもある害虫問題であり、最も代表的な問題です。生ゴミを放置すると、ハエやゴキブリなどの害虫、さらに環境によってはネズミも発生してしまいます。
特に夏場は数日放置しただけでハエが、放置時間が長いとハエが生ゴミに卵を産み、ウジが湧きます。そうなってしまうと掃除するのも大変ですし、繁殖率も高く想像しただけでもゾッとしますよね。
害虫によっては、人間への病原菌の感染源にもなると考えられています。私たちの身近にいるイエバエやクロバエは、人間に有害なバクテリアを数百種類も運んでくると結果が出ており、食中毒で有名な病原性大腸菌0-157と大きくがあることがわかっています。
腐敗臭など不快な匂いが発生する
生ゴミを放置していたら嫌なニオイが部屋に充満。そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか?生ゴミのニオイの原因は雑菌の繁殖によるもの。
雑菌は水分が豊富で温度が高くなると、より活発に繁殖するといわれています。湿気の多い梅雨や気温が上がる夏場は特に注意が必要という事です。
また、魚などの魚介類の生ゴミは、さらにニオイがキツイので放置は厳禁。強烈な悪臭を放置したままでいると、非常に不快なニオイが更に充満してしまいます。
日々の努力できちんとゴミを処分しキッチンを清潔に保ちましょう。
カビなどの原因に
生ゴミはカビの養分となる食べカスと水分を中心にできており、そのままにしているとカビ菌が繁殖する原因となってしまいます。
カビを放置しているとカビの胞子は非常に細かく、が空気中に拡散され、それらが付着することでキッチンのタイルやゴミ箱がカビてしまうことも。
更に強く拭き取ると胞子が細かい為凹凸や傷の隙間に潜り込み自力では取りきれないなんてことも。もちろん健康被害にも繋がります。
カビの胞子が体内に入ると、食中毒や肺炎、気管支炎などを起こす危険あるといわれます。食べ物を扱うキッチンにカビの胞子が飛んでいるような状態だと、衛生面でも好ましくないですよね。
ゴミに虫が湧く原因

部屋を閉め切っていても、家の中に虫を寄せ付けるものがあると、網戸などの小さなすき間をくぐり抜けて侵入してしまいます。
とくにキッチンは、水も食べ物もあるため、虫にとって格好のエサ場です。虫を寄せ付けてしまう原因は、以下のようなコトが考えられます。
ゴミに虫が湧く原因1:生ゴミの腐敗臭
 ゴミ捨て場に虫が飛んでいるのを目にしたことはあるかと思います。虫は食べ物の腐敗臭が大好物であるため、長い間放置された生ゴミは、虫を寄せ付けてしまうのです。
ゴミ捨て場に虫が飛んでいるのを目にしたことはあるかと思います。虫は食べ物の腐敗臭が大好物であるため、長い間放置された生ゴミは、虫を寄せ付けてしまうのです。
もちろん、ゴミ捨て場に限らず家庭でも同じことです。例えば、三角コーナーに野菜くずや食べ残しなどを置きっぱなしにしていると虫がやってきます。
腐敗臭を察知して潜り混んできます。また、虫が集まってくるのは生ゴミだけに限りません。飲みかけや飲みっぱなしになっている飲み物やコップにも発生します。
ゴミに虫が湧く原因2:ゴミ箱やシンクの水分

生ゴミの腐敗臭は水気があると更に強烈になります。そのため、キッチンのシンクに汚れと水分が残っていると、虫が集まってしまう可能性が高まります。
また、捨てた生ゴミから漏れ出た水分によって汚れたゴミ箱も、虫にとってはまさに天国。とくに気温が高い夏は、生ゴミが腐敗するスピードが速く、悪臭が漂いやすくなってしまいます。
ゴミに虫が湧く原因3:外に放置したゴミ

中には室内に臭いが充満しないよう、ゴミ袋ごと外に出しておく人もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、外にゴミを放置するのは虫を寄せ付けてしまう要因のひとつになっています。屋外は家の中よりも気温が高いため、生ゴミがあっという間に傷みます。
つまり、虫の発生がより深刻化する場合もあるのです。外に虫の巣を作っている状態で玄関の扉を毎日開閉していると虫が忍び込んでしまう原因になってしまうことも。
ゴミに虫が湧く原因4:袋のまま保管されたお米

お米はどのように保管していますか?お米はしっかり密閉して保管しないと、虫が発生する場合があります。袋に入れているから大丈夫という方も、油断は禁物です。
お米につく虫は、ビニール製の袋を破って侵入することもあります。気温が上昇すると、虫も活発になるため、発生リスクも高まります。
因みに例えば、ココアの粉などの粉末状態のものも同様で、コレらはお米より虫が湧く可能性が高まり、実際にお子様がココアを飲み、健康被害に遭ったケースも報告されています。
ゴミに虫が湧く原因5:排水溝の詰まり

排水溝が目詰まりを起こしていると、虫が発生してしまいます。家の中に侵入した虫が、排水溝に溜まった水に卵を産み付けることもあります。
そうなれば、虫が大量発生してしまいかねません。日ごろ何気なく行っていることが、つまりの原因となっている場合もあります。
結論1:害虫はどこから来るのか?
締め切ったはずの部屋なのに「いったいこのハエはどこから発生しているの?」と疑問に思ったことはありませんか?ハエは窓の隙間、玄関などから堂々と侵入してくる事が多いのです。
網戸をしっかりする、玄関を開けっぱなしにしない、これらの事は最低限守りましょう。ハエは網戸のほつれなどの小さな隙間からも入ってきます。
侵入を防ぐには、家の中に餌があると思わせないようにすることが肝心です。生ゴミを放置しない、食べ残しをそのままにしないなど、食べ物のニオイを残さないよう徹底しましょう。
見落としがちな排水口も疑ってください。ハエは排水口から侵入してくる事もあります。
こちらもエサのニオイを嗅ぎつけて寄ってくるので、排水口に近い三角コーナーの生ゴミの放置はNGです。また、キッチンのゴミ箱は必ず蓋つきのものにするなどニオイ対策を徹底しましょう。
それから、排水口自体が水垢や食べカスの汚れでニオイを放っている場合もあります。排水口も小まめに掃除し、清潔に保つ事でハエの侵入は防げます。
ゴミに虫を寄せ付けないために有効な対策

とは言え生ゴミを無くすことは現実的ではありません。どんなに気を付けていても、生ゴミは少なからず発生します。
しかし、処分の仕方を少し工夫するだけでも、虫が寄り付きにくくなります。次の方法を実践し、快適な環境を作りましょう。
虫を寄せない対策1:生ゴミを放置しない

虫を寄せ付けないためには、ゴミを溜めず早く処分することが大切です。生ゴミを放置する時間が長いほど腐敗が進み、臭いもきつくなります。
虫たちは生ゴミから発生する悪臭や水分に誘われてやってくるため、放置が長い程そのリスクは高くなり、生ゴミを1日放置しただけでも、コバエがたかりやすくなります。
できるだけこまめに処分し、三角コーナーや排水溝は常にキレイな状態をキープすることが大切です。もちろん、ゴミ収集日に出し忘れないことも大切です。
ほとんどの自治体では、週に2~3回の収集日なので、捨て忘れはゴミを部屋に保管する必要があります。とくに気温が高い夏は、1回忘れただけで虫がわくこともあります。
虫を寄せない対策2:生ゴミの処分方法を工夫する

できるだけ臭いを発生させないことが重要です。腐敗臭の原因となる水分をできるだけ減らして処分しましょう。
手で水気を絞るだけでも効果はありますが、生ゴミを触るのは抵抗がある方も少なくないかと思います。そこで以下の方法を試してみましょう。
✔ 生ゴミの捨て方1:新聞紙に包み、ビニール袋に入れる
読み終わった新聞紙がある場合は、生ゴミの処理に使いましょう。新聞紙に包んで捨てると、生ゴミから発生した水分が新聞紙に染み込んで、悪臭が発生しづらくなります。
また、新聞紙に含まれているインクには吸着効果があるため、臭いが抑えられるメリットもあります。新聞紙で包んだ生ゴミは、臭いや水分が漏れ出ないよう、ビニール袋に入れてからゴミ箱へ入れましょう。
✔ 生ゴミの捨て方2:ペットシーツにくるむ
新聞を取っていない方は、ペット用のトイレシートを代用すると便利です。ペットシーツはもともとトイレ用の商品のため、吸水力があり消臭加工も施されています。
そのため、生ゴミの腐敗臭や水気もペットシーツがキャッチし、臭いが漂いにくくなります。処理の仕方は新聞紙とまったく同じでです。
生ゴミをペットシーツで包み、ビニール袋に入れて処分します。ペットシーツは100枚入りで1,000円程度と手に取りやすい値段なので、生ゴミの処分用に買うのも検討してみましょう。
✔ 生ゴミの捨て方3:生ゴミのニオイにはお菓子の袋を活用
一般のポリ袋だと空気の透過率が高く、どうしてもニオイが漏れやすいのです。
そこで登場するのが「お菓子の袋」。空気の透過率は非常に低く、ポリ袋に比べ、1000分の1ほどといわれています。これは、生ゴミ対策に活用しない手はありません!実際に試してみました。
いらない紙で水分を吸収した生ゴミを、ポリ袋へ。
さらにそれらを、お菓子の袋に入れます。
ニオイが全然漏れません。大きめのお菓子の袋に溜めてゴミ回収日を待ちます。
ただし、この方法は注意点が一点あります。ゴミ回収日には中の生ゴミだけ出して捨てるようにしてください。お菓子の袋はプラスチック製容器包装なので資源ゴミになります。
キチンとゴミの分別をして捨てましょう。こちらの方法は、家にあるゴミを再利用することで簡単にできてしまうので、かなりオススメです。
✔ 生ゴミの捨て方4:生ゴミを冷凍庫で保存する
ゴミ収集日まで日数がある場合、旅行などで留守にするとき、ゴミをどうしようか悩むことはありませんか?新聞紙やペットシーツにくるんでも、臭いを抑えられるのは数日。
ゴミをすぐに捨てられない、そんなときは生ゴミを冷凍してしまいましょう。
冷凍すると腐らないので臭いも発生しません。しかし、冷凍庫に生ゴミを入れることに抵抗がある方もいるかと思います。そのような場合は、ジップロックなどで密閉し、保管場所を分けてみましょう。
長期不在時の害虫発生を防ぐために出かける前は家の排水口に蓋をして出かけましょう。コバエは排水口からも侵入してきます。
不在中に生ゴミのニオイが漏れていて、家に帰るとコバエが大量発生なんてことになっていたら、恐ろしいですよね。排水口の蓋には、ダイソーに売っているシリコンラップがオススメです。
虫を寄せない対策3:フタ付きのゴミ箱を使う

できるだけ臭いが漏れ出さないゴミ箱を使うことも有効な対策です。フタ付きのゴミ箱は、臭いが外にも漏れにくい上に、虫が侵入しづらいメリットもあります。
ゴミ箱用の防臭剤や防虫剤を併用すれば、より効果的です。
虫を寄せない対策4:防虫剤を設置する

とは言え、生ゴミの臭いが漏れないように気を付けていても、虫は一瞬のスキをついて侵入してきます。虫をできるだけ家に入れないためには、防虫剤が便利です。
玄関や窓など、虫が入ってくる可能性が高い場所には、必ず設置しましょう。玄関用に吊り下げられる防虫剤や、外置き用のゴキブリ駆除剤も市販されています。
窓には、網戸に取り付け可能な防虫剤を付けると効果的です。コバエが発生しやすいキッチンには、コバエ専用の駆除剤を置いておきましょう。
駆除剤には、テープに粘着させるものや、感電させて撃退するものなど、いろいろなタイプがあります。誘因ゼリーが入った駆除剤は、置いておくだけでコバエが集まる上に、そのまま捨てられるので便利です。
駆除剤はコバエが発生しやすい三角コーナーの近くに置いておくと、より効果が高まります。お米には、米びつ専用の防虫剤を入れておくと、コクゾウムシの発生を防げます。
小さな子どもがいる場合は、ハーブ由来の商品を選ぶと安心です。
虫を寄せない対策5:シンクを清潔に保つ

虫の発生を防ぐためにも、キッチンの清潔を保つことが重要です。食材の残りやカスがシンク内に残っていたり、付着したままになっていたりすると、虫を引き寄せる原因となってしまいます。
ぬめりを除去し、食べ物のくずを残さないよう、こまめに掃除を行いましょう。シンクは、ブラシと漂白剤があれば手間なく簡単にキレイになります。
キッチン周りの片付け・清掃は業者の利用がオススメ

既に『強烈な匂いや汚れが目立っている。片付けたいけど何か清掃できる方法はないの?』といったお悩みもあるでしょう。
結論からお伝えすると、頑固なキッチン周りの汚れを清掃し片付けるなら清掃業者を利用する事で短時間かつ確実に綺麗にする事が可能です。
そこで、ポイントとなるのが片付け業者と清掃業者は作業できる事が違うため、2つの業者に分けなければならない事もあります。
しかしリ・バスターなら、キッチンまわりのハウスクリーニング・清掃のみならず、キッチンまわりの片付けや不用品回収、粗大ゴミの処分とセットでハウスクリーニングや消臭作業も対応可能です。
キッチンまわりの虫のストレスやニオイの問題はキッチンまわりの片付けとハウスクリーニングがセットで行えるリ・バスターにお任せください!
キッチン回しの片付けや清掃の問題ならリ・バスター

キッチンまわりのニオイや虫が湧く問題について、キッチンまわりの片付けや不用品回収、ハウスクリーニングなどセット作業が得意なリ・バスターへ24時間365日お気軽にご相談ください。予算なども考慮して最適な片付け・清掃をお約束します。
無駄な費用はありません
リ・バスターなら無駄な追加料金や初期費用、基本料金はありません。例えば、以下のサービスが全て含まれています。
✔ 見積/出張費/基本料等ありません!
✔ 分別/整理/解体/清掃/貴重品の探索
✔ 廃棄物処理/基本清掃作業/運搬作業
全てコミコミ価格で安心の明朗会計!これだけではなく、更にこのようなメリットで皆様に大変ご好評頂いております!
✔ 最速/安心丁寧で選ぶなら当社
✔ 初期費用/追加料金は必要なし
✔ 頭金不要/分割払いも対応可能
✔ 明朗会計/好評安心定額パック
✔ どんな不用品もまるごと回収!
✔ 限定割引/24時間365日相談可
✔ お客様第一主義/柔軟かつ迅速
✔ 資格など取得済みの優良業者
ゴミ屋敷状態のキッチンまわりでも片付け・清掃OK!またゴミ屋敷状態のお部屋の片付けとセットでお部屋のニオイや虫が湧く問題にも対応いたします!
一人では片付けられない、キッチンまわりのニオイや虫が湧く問題を解決したい!このようなお悩みをお持ちの方!
信頼できるキッチン周りの片付け業者利用が安心
弊社リ・バスターはこれまで皆様に大変ご好評頂いております。片付けは業者のスキルにより時間が大きく変わります。
キッチン周りにゴミや不用品を長い間溜めてしまうと、キッチン周り汚れ放置期間が長いほど汚れや匂いは進行し手に負えなくなってしまいます。また、キッチン周りの状態が進行するほど作業の時間、労力、費用もかかります。
弊社はキッチン周りの片付け・清掃のプロ集団ですので、短時間で作業完了するため、余計な費用をかける事なく高品質かつ料金も安く抑えることができます。
キッチン周りをご自身で片付ける事が困難でも、業者を利用しリセットすることで、早期のキッチン周りの虫が湧く・匂いの問題の解決が可能です。
ゴミ屋敷状態でもOK!キッチン周りの片付け掃除のプロ集団専門業者リ・バスターなら作業丸ごとOK!
【なぜ虫やニオイが湧く!?】キッチン周りのゴミの片付け・清掃はリ・バスター
https://re-baster.com/campaign/housecleaning/